Books-Science: 2009年3月アーカイブ
・次元とは何か―「0次元の世界」から「高次元宇宙」まで (ニュートンムック Newton別冊サイエンステキストシリーズ)
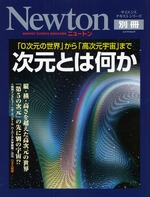
次元の考え方から最新宇宙論までをビジュアル解説。ニュートン別冊。
デカルトは次元を「1点の位置を決めるために必要な数値の個数」と定義した。1次元(線)なら距離Xだし、2次元なら座標X、Y、3次元なら座標X、Y、Zで、1点の位置を決定することができる。
ユークリッドの『原論』は、次元を
立体(3次元)の端は面(2次元)である。
面(2次元)の端は線(1次元)である
線(1次元)の端は点(0次元)である
と定義した。しかし、こうした定義では3次元を超える次元を説明できない。アリストテレスは「立体は"完全"であり、3次元をこえる次元は存在しない」とまで論じていたという。
19世紀の数学者アンリ・ポアンカレは、ユークリッドを逆手にとって、次元を次のように定義し直した。
端が0次元になるものを1次元(線)とよぶ
端が1次元になるものを2次元(面)とよぶ
端が2次元になるものを3次元(立体)とよぶ
端が3次元になるものを4次元(超立体)とよぶ
この調子で5次元、6次元、無限次元までを定義することが出来るようになった。これは「点を動かすと線ができ、線を動かすと面ができる。このように、ある次元の図形を、その次元に含まれない方向へ動かすことで、もとの次元より一つ高い次元の図形をつくることができる。」ということでもある。よって立方体を動かせば4次元の超立方体ができるのだ。ただし3次元空間に含まれない方向へ動かす必要がある。
こうした次元の考え方の基礎から始まって、アインシュタインによる4次元時空論、力の統一、超ひも理論、ブレーン理論、巨大加速器LHCの実験の話までを、美しい概念図やイラストたっぷりに、かみ砕いて教えてくれる内容。
これを読み終わると、この世界は4次元(3次元+時間)ではなくて、実は10次元なのだという最新物理学の仮説の意味が理解できる。残り6つの次元は極小レベルで折りたたまれているのだ。ワープする余剰次元モデルを提唱するリサ・ランドールの長文インタビューを巻末に収録している。
わかったふりをしてきた部分が、要点整理とビジュアルで本当にわかる本だった。宇宙論の本の副読書としておすすめ。
「生物と無生物のあいだ」の分子生物学者 福岡伸一氏の科学読み物。「生命とは動的な平衡状態にあるシステムである」という主題周辺でエッセイが8章。
人は毎日カツ丼ばかり食べているとカツ丼になってしまう、わけではない。だがカツ丼を構成している分子は、身体の構成分子と交換されてしばらく一部となり、やがて外へ抜けていく。分子は入れ替わるがシステムは維持される。こうした分子の流れ、動的な平衡状態こそ生命の本質なのだということをルドルフ・シェーンハイマーという科学者が1930年代に突き止めていた。
「個体は感覚としては外界と隔てられた実体として存在するように思える。しかし、ミクロのレベルでは、たまたまそこに密度が高まっている分子のゆるい「淀み」でしかないのである。」
流れであり平衡状態であるという見方は、東洋医学的な見方でもあるなと思う。患部を部分的に治療するのではなく全体を整えることで、治る。生物の構造はDNA設計図をもとに複製された大量のミクロ部品から構成される複雑な機械という側面もあるが、生きている生命にはそうした構造に還元できない現象も多い。
「ここで私たちは改めて「生命とは何か?」という問いに答えることができる。「生命とは動的な平衡状態にあるシステムである」という回答である。 そして、ここにはもう一つの重要な啓示がある。それは可変的でサスティナブルを特徴とする生命というシステムは、その物質的構造基盤、つまり構成分子そのものに依存しているのではなく、その流れがもたらす「効果」であるということだ。生命現象とは構造ではなく「効果」なのである。」
つまり生命とは絶え間ない水流が作り出す渦巻きみたいなものということだ。水が勢いよく流れている間は実体であるかのように立ち現れるが、基盤は流れる水分子に過ぎない。こうした生命の動的平衡の特徴的な性質について面白い説明が続く。たとえばシグモイド・カーブの話。
「生命現象を含む自然界の仕組みの多くは、比例関係=線形性を保っていない。非線形性を取っている。自然界のインプットとアウトプットの関係は多くの場合、Sの字を左右に引き伸ばしたような、シグモイド・カーブという非線形性をとるのである。」
音量ボリュームのダイヤルを回すと最初は音がいきなり大きくなったように聞こえるが、あるレベルを超えるとさらに回しても大きな音は大きな音に過ぎなくなる。インプットとアウトプットの関係が比例関係でなく鈍ー敏ー鈍という変化をするものだそうだ。インプットが小さい領域では立ち上がりが低い。高い領域では高い。これなどはビジネスマンがサービスやインタフェースの設計に何か応用できそうな話である。
最新の分子生物学の成果を一般人向けのわかりやすいエッセイとして読めて楽しい。
・生物と無生物のあいだ
http://www.ringolab.com/note/daiya/2007/07/post-598.html
2007年サントリー学芸賞受賞。

