Books-Science: 2012年1月アーカイブ
・明日をどこまで計算できるか?――「予測する科学」の歴史と可能性
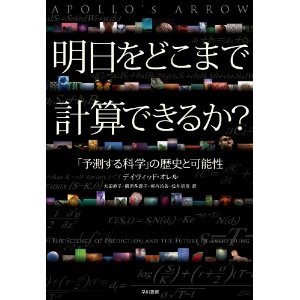
天候、医療、経済の3つの領域における科学的な予測の可能性を検証した読み応えのある本。複雑な事象に関する未来予測は、数学や確率の言葉という客観の仮面を被った主観的意見に過ぎないことを明らかにしてみせる。
明日が晴れか曇りかの簡単な天気予報はできても、次の大きな嵐がいつ来るかは予測ができない。次のインフルエンザの流行や株価の大暴落も同じだ。予測はモデルをベースにするが、科学者、専門家がつくったモデルに対する信頼性をもっと疑ってかかるべきだと著者はいう。
予測モデルは方程式の組をもとにしている
↓
しかし、根本的なシステムを方程式に還元することはできない
↓
こうしたシステムのモデルは、パラメーターの変化に敏感な傾向がある
モデルが精巧になればなるほどパラメーターの不確実性は増加していく。そして複雑な系は初期値の小さな違いに敏感だ。現実に取得できるパラメーターには種類も精度も限界がある。
そして著者が指摘するもうひとつの予測不可能の原因はシステム内の局所が相互に影響して、現象を創発している場合だ。雪や嵐、株価の急騰急落、パンデミックは、システムの創発特性とみなせるものであり、第一原理からの計算で導き出せないのだという。
主にそのふたつの原因により、科学者が方程式の組でつくる予測モデルは、過去の出来事に合わせることはできても、予測の精度が向上することがない。「私たちはどうやら、未来は過去に似るという思い込みの罠に陥っているようだ。」。
もちろん簡単な予測、だいたいの目安が有益に機能する分野もある。直近の天気予報はだいたい当たるし、メールのスパムフィルターも予測モデルだし、回転ずしで何を流すかだって予測モデルでうまくいっているらしい。どこまでが予測可能でどこからは予測が無効なのかの線引きが重要なのだ。
