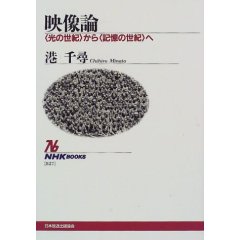映像論―「光の世紀」から「記憶の世紀」へ
「わたしたちは文字通り「映像の地球時代」に生きている。地球上のどこにいても、特定の地域の特定の情報を、いながらにして手に入れることが技術的に可能なのだ。」
テレビやインターネット、DVDを通じて、私たちはおよそ考えられる限りの映像を入手可能になった。その状況を著者は「ピクチャープラネット」と呼び、写真誕生から現在までの映像史を振り返るとともに、「そこでは見るという行為が、身体的な移動の経験と切り離されて、独立してしまう危険が常にある。」と問題提起をしている。
写真や映画は大衆心理の操作の道具として、前世紀から利用されてきた。戦争報道の写真を新聞に掲載したり、犯罪者のモンタージュで優生学の正当性を主張したり、プロパガンダは映画を積極的に取り込んだ。誰かが作り出す「スペクタクル」映像を人々は信じるようになった。
フランスの思想家ギー・ドゥボールが1967年に「スペクタクルの社会」の中で
「スペクタクルは、社会そのものとして、同時に社会の一部として、そしてさらには社会の統合の道具として、その姿を現す。社会の一部として、それはあらゆる眼差しとあらゆる意識をこれみよがしに集中する部分である。この部門は、それが分離されているというまさにその事実によって、眼差しの濫用と虚偽意識の場となる。」
と書いている。
これはピクチャープラネット化が進んだ現在、ますます重要な問題だと思う。たとえば世界で最近起きていることは無数にあるが、テレビが報道する映像の長さや頻度で、私たちはそれぞれの事件の重大さをとらえがちである。今がどんな時代かという同時代イメージもまた映像に強く影響されていると思う。
この本では、映像とは何かを、映像技術、記憶、身体性などの観点から歴史的に整理して、映像社会の問題を指摘する。
エピローグに登場する、全盲の写真家ユジュン・バフチャルのエピソードは印象的だった。
眼が見えない写真家がカメラを向けると、撮られる人の顔がこわばることを、彼は知っていて逆手にとっている。音などを頼りに自らレンズの絞りを合わせる。撮影後はコンタクトプリントをつくり作品を選ぶ。その作業は対話の中で行われる。そうしてできた写真を彼自身は見ることはない。しかし彼は自分が見たものを信じている、共同作業を信じている。強い印象を持った作品が次々に出来上がる。社会的な盲目状態の人たちと比べて、何倍も見ることを意識している。