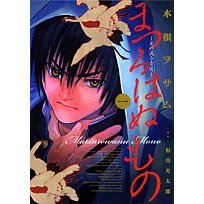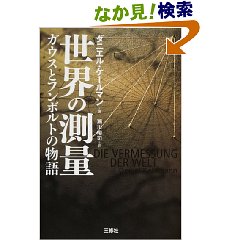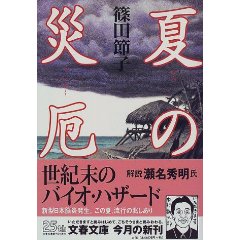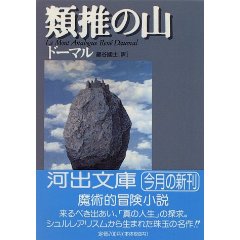Books-Fiction: 2008年7月アーカイブ
恒川光太郎の「夜市」「雷の季節の終わりに」につぐ期待の3作目。
3本の短編を収録。
「秋の牢獄」
「これは十一月七日の水曜日の物語だ」。目が覚めると昨日はなかったことになって、再び同じ秋の1日を繰り返してしまう不思議世界の物語。
「神家没落」
日本の各地に神出鬼没する因縁の家に閉じこめられた男が異世界からの脱出方法を探るが...。
「幻は夜に成長する」
念じた相手に思い通りの幻覚を見せる霊狐の力を受け継いでしまった少女の物語。
異界モノでは既存の神話や伝承をベースにする作家が多い中で、恒川光太郎はかなり独創的な異世界モノを追求している。この3本はどれも異次元や超能力がテーマだ。神話や伝承の豊穣なイメージに敢えて頼らず、海外のハードSF作品に通じるような普遍性の物語の方へ向かう作家のように思える。案外、グレッグ・イーガンなどの影響を受けているのだったりして。
大作家になる予感を感じて注目している恒川光太郎、3冊目も期待通りハイレベルな内容だったが、次は小説家としての記念碑的な、決定的な長編を出してほしい。
第一作「夜市」収録の名作「風の古道」は漫画になったようだ。夜市』は円谷エンタテインメントで映画化が決定しているらしい。
・夜市
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004796.html
・雷の季節の終わりに
http://www.ringolab.com/note/daiya/2006/11/post-489.html
「世界の測量」は小説である。ドイツ国内で130週間に渡ってベストセラー(35週は1位)に入り120万部を売り上げ、世界45カ国語に翻訳された。2006年度に「ハリーポッター」や「ダ・ヴィンチ・コード」をおさえて世界で2番目に売れた驚異的セールスの本である。
近代地理学の祖 アレキサンダー・フォン・フンボルト(1769-1859)と、数学の王 カール・フリードリヒ・ガウス(1777-1855)という、二人のドイツが生んだ大天才の、数奇な人生を描いている。
タイトルの「測量」は世界の大きさや自然の仕組みを発見しようとする人間の行為を象徴している。現代の先端科学は未知の世界を測るには巨大な粒子加速器や宇宙船を必要とするようになってしまった。天才といえど発見は一人ではできなくなった。フンボルトとガウスが生きた18世紀中頃から19世紀中頃は、人間が世界を自らの身体と頭脳で測ることができた最後の時代だったのである。
二人の天才の行動パターンは対照的だった。探検家として未踏の世界へ決死の旅に出て測量を続けた行動派のフンボルト。実測データで世界の姿を示そうと冒険旅行に半生を費やした。ガウスもドイツ国内で測量の仕事をしていたが本当の関心は数学や天文学にあった。言葉を話すより前に計算ができたという神童伝説で知られるガウスは計算や思考を重要視していた。引きこもり型であった。
世界を測るアプローチと活動領域は異なる二人だったが厳格にして頑固に真理を探究する姿勢はそっくりだ。そして共にその性格があったが故に、現代自然科学の礎となる大発見の数々を成し遂げた。二人の偉業は世界史における「ドイツ的なもの」の最高到達点だった。(それがこの本がドイツで爆発的に売れた理由ではないだろうか。ドイツでの大ブームは国の歴史的英雄を取り上げたNHK大河ドラマみたいなもの、かもしれない。)
フンボルトの動的な章と静的なガウスの章が交互に配置されている。どちらも天才であるが故に許された自分勝手の奇人変人であり、物語を彩るエピソードにはことかかない。テンポが良くて読みやすい「哲学的冒険小説」。
東京郊外で突然発生した日本脳炎らしき感染症が異常な速度で患者を増やしていく。撲滅されたはずの病の突然の復活に、対応におわれる市の保健センター職員と看護婦らの奮闘を描くパニック小説。
この作品には特効薬を開発する医者だとか、危機一髪でワクチンを届ける救急隊員のような、派手な活躍をするヒーローやヒロインは一人も出てこない。感染防止と原因究明のために力を尽くすのは市役所や病院という大きな組織の末端にいる人々。彼らが戦う相手は病原菌やウィルスではなく、前例がないことには意志決定ができない硬直化した官僚制度であった。篠田節子は八王子市役所に勤務していた体験を活かして、リアルに市と病院の現場の動きを描写している。
現代人が感染症で死ぬ確率というのは、テロや原子爆弾で死ぬ確率よりも遙かに高い。メディアがあまり取り上げないけれど、世界にとって自分にとって最大の脅威のはずだなあと思って興味を持って関連書を読んできた。この作品はこうした本が警告する危機を、説得力たっぷりに描いている。
・感染症―広がり方と防ぎ方
http://www.ringolab.com/note/daiya/2007/01/post-511.html
・感染症は世界史を動かす
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004403.html
・インフルエンザ危機(クライシス)
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004247.html
・世界の終焉へのいくつものシナリオ
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004729.html
上記の本で少し取り上げられていた学童への予防接種反対論をこの本で詳しく知った。大規模な感染で多数の死者を出すことを考えれば、集団への予防接種は有効な手段のはずなのだ。
しかし生ワクチンによる予防接種は、少量の病原体を身体に入れるという原理上、数万人~数十万人に一人くらいの小さな確率で感染者を出してしまう。市がそれを強制的にまたは無料で実施すれば、市は万が一の自体に対して責任を負わされる。だから、市民各自の費用で任意接種の方が無難ということになってしまう。結果としてパンデミックを防げない状態になってしまう、らしい。この作品の中でも予防接種反対論の壁と主人公達は戦っている。
地味だが極めてリアルなパニックホラー。この病の最盛期は夏なので今が読み頃。
今年は篠田節子をたくさん読んでいる。以下。
・レクイエム
http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/05/post-752.html
・カノン
http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/04/post-740.html
・弥勒
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/005292.html
・ゴサインタン―神の座
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/005260.html
・神鳥―イビス
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/005177.html
「凍える森」は20世紀前半に発生したドイツの大量殺人事件を題材にした小説。
ドイツミステリー大賞受賞で今年映画化が決まっている。
現実の事件の情報は、Wikipediaにも掲載されていた。研究サイトもある。
・ヒンターカイフェック事件 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BA%8B%E4%BB%B6
「ヒンターカイフェック事件とは、ドイツ史上最も謎の多い犯罪として知られる殺人事件。ヒンターカイフェックは、 バイエルン州の都市インゴルシュタットとシュローベンハウゼンの間(ミュンヘンの約70キロメートル北)にあった小さな農村。1922年3月31日の夕方、村の農場の住人6名がつるはしによって殺害された。事件は現在も解決されていない。6名の犠牲者は、農場の主人の男性(63歳) とその妻(72歳)、夫妻の娘(35歳、未亡人)とその子供2名 (7歳の女の子と2歳の男の子)、そして農場の使用人の女性である。」
そして「何年にもわたり100名以上が容疑者として尋問されたが」事件は未解決のまま現在に至る。この小説は近隣住民の証言集として構成されている。証言は語り口調で2,3ページと短いのでペースよく読み進められる。ときどき犯人視点の断章が挟み込まれる。証言の言葉の含みや矛盾をたどって真犯人を見つけ出す推理小説の醍醐味が最後の数ページまで味わえる。
宗教と因習にとらわれた農村の息苦しいムードが全体に漂う。一言で言うとドイツ版の八墓村。人間関係が密な村社会にあって被害者一家は人づきあいを嫌うはぐれものだった。証言が重ねられるたびに、少しずつ事件の全貌が明らかになっていく。暗い闇の向こうに知られざる一家のおぞましい秘密があることが見え始める。
伏線や隠し方が巧妙で何度か読み返して楽しめる名推理小説。
「はるかに高く遠く、光の過剰ゆえに不可視のまま、世界の中心にそびえる時空の原点―類推の山。その「至高点」をめざす真の精神の旅を、寓意と象徴、神秘と不思議、美しい挿話をちりばめながら描き出したシュルレアリスム小説の傑作。」
1944年に36歳で夭折したシュールレアリスム作家ルネ・ドーマルの代表作。20世紀の奇書。私たちは道を極めようとするときそのプロセスを登山にたとえる。究極の理想、神の領域に向かって登る。しかし、その至高点は、生身の人間にとって目指すことはできるが現実には到達しえない象徴的存在「類推の山」である。
主人公は雑誌「化石評論」に天と地を結ぶ山についてエッセイを書いた。旧約聖書のシナイ山、エジプトのピラミッド、ギリシアのオリュンポス、バベルの塔、中国の神仙の山々など世界の神話伝承には人間が神性に高まりうる通路としての「類推の山」が存在しているという内容だ。
この記事に読者から一通の手紙がやってきて物語が始まる。
「前略、あなたの<類推の山>についての記事を読ませていただきました。私はいままで、自分こそあの山の実在を確信するただひとりの人間だと信じていたのです。今日、それが私たち二人になったわけで、明日は十人、いやもっとふえるかもしれない─── そうなれば探検を試みることができるでしょう。私たちはなるべく早く接触をもたなければなりません。よろしければすぐにでも下記の番号のいずれかにお電話ください。お待ちしています。」
こうして、探検隊が結成され、一行はエベレストよりも高い天にも届く高峰を探す。存在するはずのない場所への長い旅始まる。それは「別の事物、彼岸の世界、異なる種類の認識」を求めたドーマルの魂の自伝でもあった。
物語はドーマルが執筆途中で肺結核で死んだため、類推の山に至る旅は第5章で未完に終わっている。だが、ドーマルの妻と仲間の作家がその事実を明かす「後記」と「覚書」を追加したことで作品としての完成度は高まった。物語の中断がドーマル自身が道半ばにして倒れたことと二重写しに見えて、作家の当初の意図以上にシュールな作品となったのである。象徴の山の頂は人間には登れないものなのだ。
神話的な物語なので今読んでも古さを感じない。全編が美しいメタファーに満ちている。
・「百頭女」「慈善週間または七大元素」
http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/06/post-771.html
こちらも20世紀シュルレアリスムの奇書。