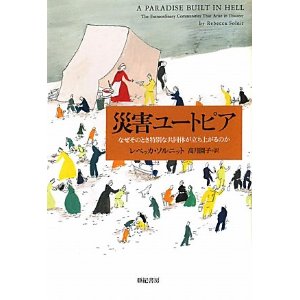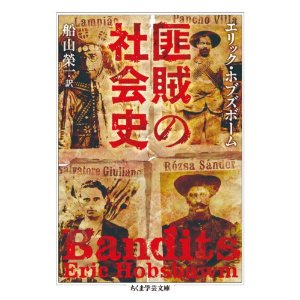Books-Sociology: 2011年3月アーカイブ
「希望学」の提唱者で東大社会科学研究所教授 玄田有史氏の近刊。
「希望は「気持ち」「何か」「実現」「行動」の四本の柱から成り立っている。希望がみつからないとき、四本の柱のうち、どれが欠けているのかを探す。」
希望学では希望を、
「行動によって何かを実現しようという気持ち」
Hope is a Wish for Something to Come True by Action.
と定義している。
幸福は継続を求めるが、希望とは変化を求めるものだ。過去数十年のニュースにおいて「希望」と一緒にでてくる言葉のトップは「水俣」(病)だったそうだ。苦しい現実、過酷な状況を良い方向に変えたいと願う気持ちが、希望には宿っている。
日本の大人の3分の1は希望がない、もしくは諦めているというデータがあるそうだが、逆に考えると多くの人は希望を持っている。その中身を知るべくアンケートをとると、家族・健康・遊びよりも、仕事にまつわる希望(66.3%)が一番多いのだそうだ。希望格差社会という言葉があるが、現代において希望が持てない若者が増えたのも、不況で安定した雇用につけないことに大きな原因があるのは間違いない。
収入と希望は年収三百万円以上では相関しないとか、やりたいことを目指していたけど途中で変化した人の満足度が高いとか、仕事と希望についての真実がいくつも明かされる。「いつも会うわけではないけれど、ゆるやかな信頼でつながった仲間(ウィーク・タイズ)が、自分の知らなかったヒントをもたらす。」というソーシャルグラフの大切さも強調されている。
著者によると希望を構成する3大要素は「可能性」、「関係性」、「物語性」。物語性というのは、自分の人生の物語を意識している人は、紆余曲折も無駄な努力も糧と出来るので強いということ。挫折を乗り越えた人のほうがそうでない人よりも、希望を持っている割合が高いというデータで裏付けされている。失恋経験が乏しい20代男性は恋愛や結婚をあきらめやすいなんて話も。
著者が講演で中学生、高校生たちに話したアドバイスが印象的だった。頑張って壁を乗り越えなさいなんて言わない、壁は乗り越えられないから壁なのだと前置きしたあとで、
「大きな壁にぶつかったときに、大切なことはただ一つ。壁の前でちゃんとウロウロしていること。ちゃんとウロウロしていれば、だいたい大丈夫」
希望とは模索そのもの。努力してみる、やりながら考えること、そのプロセスに希望が宿るのであり、無駄な努力と諦めるところには希望はないという。
ネットエイジの西川社長らが「希望」という名の救援・復興支援プロジェクトを始めた。私もまずは「いいね!」を押して参加することにした。実は西川さんがこの本に影響を受けたというFacebookの書き込みをみて、私はこの本を読んだのだ。
希望学から生まれた希望という名のプロジェクト、みなさんも参加しませんか。
震災地の救援・復興支援「Project KIBOW」を発足。世界との架け橋に
http://www.venturenow.jp/news/2011/03/18/1848_010380.html
左翼地下活動が盛んな前世紀初頭の「スパイ」の時代、飛行機と空爆による「みなごろし」の時代、監視カメラとゲーテッドコミュニティの「プライベート・セキュリティ」の時代。3つの時代の3つのキーワードを軸にして、人が人を信じないということ、監視テクノロジーの関係性を探る社会史。
技術と人間不信は補完関係にある。たとえば銀行のATMには、暗唱番号認証と監視カメラが当たり前についてくる。私たちは自分が社会に疑われていること、相手から信用されていないことについて鈍感になっていると著者はいう。そして機械化によって人は目を合わせることがなくなると、人間は反社会的な行動をとりやすくなる。戦争では、遠隔からの爆撃技術によって、人が人をためらいなく殺せるようになった。機械の目には功罪の両面がある。
監視技術はふつうでないものを発見する技術だが、公共空間においてはふつうこそ疑わしいという話が面白かった。社会学者のアーヴィング・ゴッフマンの「ふつうの外見」という概念が紹介されている。
「攻撃の意図を隠す側と、意図に気づいているものの、それを隠している側とは、いずれも「ふつうの外見」をとる。このとき、「ふつうの外見」は、もっとも疑わしい。個人は、自分の周囲にいる「ふつう」の他者をすべて疑わざるをえなくなるのだ。こうなってしまうと、その人をとりまく世界は、熱い(Hot)ものになる。ゴッフマンは、<Hot>という単語を使っているが、これは、攻撃者が迫っていて危険だというような意味と読める。 にもかかわらず、私たちは、この「ふつうの外見」を用いなければ、相手に対して「攻撃の意図がないこと」を伝えられないのである。同様に、相手が攻撃してくるのではないかと「疑っていないこと」を示すこともできない。」
「個人は、ふつうの外見の背後で、逃走したり、またもし必要なら再び争いに戻ってくる用意をしている」。未知の相手と場を共有するということは、ある種のだましあいであり、これが負の相互作用になることもあれば、秩序維持にはたらくこともある。結局はそこで生きる人々のこころの在り方が社会の性格を変えてしまう。心の武装解除、賭けとしての信頼に賭けてみること、目を合わせることの重要性が、重要なのだ、歴史から学びなさいというメッセージがある。
第一章で描かれた20世紀前半のスパイというのは、とても人間臭くて監視する方もされる方も、人の目を意識する仕事だったことがよくわかる。ある意味人間的な監視社会だ。次第に機械の目がその監視を代行するようになると、人間性のリミッターがはずれて、監視対象をヒトではなくモノとして扱うようになる。安全やコストのためといって高度化されてきた監視社会の危うさを改めて認識させられる本だ。
大爆発、大震災、大洪水、テロ。大災害が発生した直後には、必ず人々の助け合いのコミュニティが出現する。無償の愛で困っている人を助け、絶望している人を励ます。普段は眠っていた人々の創造性が発揮される。その特別なコミュニティのことを著者は災害ユートピアと呼ぶ。
サンフランシスコ大地震、ハリファックスの大爆発、ロンドン大空襲、メキシコシティ大地震、9.11同時多発テロ、ハリケーン・カトリーナ...。歴史的な大災害やテロの直後に生成された災害ユートピア事例を研究し、なぜ人々は地獄のような光景の中にユートピアを作りだせるのか。そして、なぜそうしたコミュニティが永続せず、つかの間のパラダイスに終わってしまうのかを探究する。
現実の大きな災害直後の市民の特徴は冷静沈着だ。パニックになる確率はゼロに近い。人々は混乱のさなかにも、冷静に救助活動を開始し、生存確率を高めるために柔軟に行動していた。人々がが下敷きになったがれきの山の一番近くにいるのは、救急隊員でも警察でもなく、一般市民なのだ。
ハリケーン・カトリーナの直後に、略奪やレイプは実際にはほとんど起きていなかった。火事場泥棒もいないのだ。そうしたデマを流したのはメディアであり、問題を引き起こしたのはそれに煽られて行動した為政者や警察、軍隊であった。警察はニュオーリンズから出る橋を監視して、逃げてくる黒人の市民を銃で威嚇し、危険な街に閉じ込め、犠牲者を増やした。
過去の災害を調べても、市民を暴徒とみなして射殺するとか、強制収容所のような場所に閉じ込めるなど、市民ではなく軍隊や警察官が犯罪を起こしていた例が多い。エリートたちは、一般の人たちがパニックになると思い込んでパニックに陥る。自分の身を守るために凶暴で野蛮な人間を排除しようとする。メディアも誤った報道でパニックを煽る。権力を持っている分、エリートのパニックは災害後の混乱に大きな悪影響を及ぼす。
人間は危機に際して、本質的に利他的であり、冷静に行動できるのに、エリートのパニックと、メディアの思い込み報道が、災害ユートピアの可能性を妨害していると著者は指摘している。
「災害は、世の中がどんなふうに変われるか───あの希望の力強さ、気前の良さ、あの結束の固さ───を浮き彫りにする。相互扶助がもともとわたしたちの中にある主義であり、市民社会が舞台の袖で出番を待つ何かであることを教えてくれる。」
中世以降の世界史における匪賊(ひぞく)=ソーシャル・バンディットの果たした役割を分析する本。1969年出版で、訳書がみすず書房から出ていたのが、このたびちくま学芸文庫から復刊された。匪賊は義賊とも訳される。
「義賊についての要点はこうである。彼らは領主と国家によって犯罪者とみなされている農民無法者ではあるが、農民社会の中にとどまり、人々によって英雄、あるいはチャンピオン、あるいは復讐者、あるいは正義のために闘う人、あるいはおそらく解放の指導者とさえ考えられており、いずれのばあいにせよ、称賛され援助され支持されるべき人々と考えられていたことである。」
匪賊の代表格はロビン・フッドやジェシー・ジェームズである。貴族強盗、復讐者、ハイドゥク、収奪者などの類型が示されるが、政府から見ると犯罪者なのだが、それなりの大義や主張、そして大衆の人気を背負って組織的に活動するアウトローのことである。抑圧的権力に対する反抗の姿勢を示し、正義を求めた闘争を戦い、貧しい民衆の味方となるのが、匪賊だ。
若き毛沢東も「梁山泊の英雄たちに倣え」と言って紅軍ゲリラを組織したそうだが、梁山泊は『水滸伝』のなかに登場する匪賊集団である。彼らは時に政府軍の兵士を殺したり、富める者から収奪を行うので犯罪者、危険因子という側面もある。基本は奔放な荒くれ者であるから、組織統制になじまず、社会革命の本流を担うには非力で、一時的な存在でもあった。
工業化された社会では匪賊は存在しえないため、もはや伝説上の存在に近い。だが匪賊の生きざまには、自由、ヒロイズム、正義の夢、無邪気と冒険という物語性に満ちていたため、小説や映画のようなかたちで現代においても語り継がれるケースも多い。
古今東西の匪賊の研究で明らかになる事実のひとつとして、その理想的な単位は二十人以下であったという分析がある。その理由は、「たいていの現地首領にとって大きな兵員を装備させることや、あるいは強力な個性が直接統制しうる範囲を超えて部下をさばくことが、基本的にはできないことを示すものである。」というものだが、ゲリラ闘争をやるなら、20人以下でやるべきというノウハウでもあるのかもしれない。